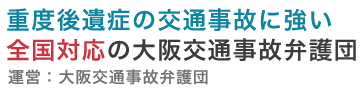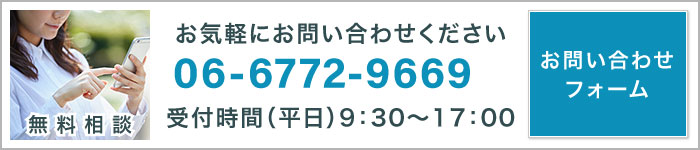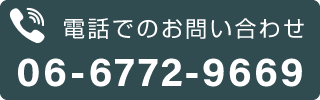脊髄損傷による障害は、麻痺の範囲及び程度、食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な身のまわりの処理動作についての介護の要否及び程度に応じて、原則として、1級から12級まで、7段階に区分して等級認定がなされます。
1.麻痺の範囲
麻痺の範囲は、以下のとおり区分されます。
|
四肢麻痺 |
両方の上肢と下肢の麻痺 |
|
片麻痺 |
片方の上肢と下肢の麻痺 |
|
単麻痺 |
上肢または下肢の一肢の麻痺 |
|
対麻痺 |
両方の上肢または両方の下肢の麻痺 |
2.麻痺の程度
麻痺の程度は以下のとおり、区分されます。
高度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(立ったり歩いたり、物を持ち上げて移動させたりすること)ができない状態をいいます。
<例>
- 上肢の場合
三大関節と5本の指の全ての関節を自身の力で動かすことができない、又はこれに近い状態 - 下肢の場合
三大関節の全ての関節を自身の力で動かすことができない、又はこれに近い状態
中度 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限がある状態をいいます。
<例>
- 上肢の場合
障害を残した一上肢では,仕事に必要な軽量の物(概ね500グラム)を持ち上げることができない,あるいは文字を書くことができない状態 - 下肢の場合
一下肢に障害を有するため,杖もしくは硬性装具なしに階段を上ることができない、あるいは両下肢に障害を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難である状態
低度 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度損なわれている状態をいいます。
<例>
- 上肢の場合
障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴う状態 - 下肢の場合
日常生活はおおむね一人で歩けるが,一下肢に障害を有するため不安定で転倒しやすく速度も遅い場合,または両下肢に障害を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができない状態
3.後遺障害等級の認定基準
以下のとおり、自賠責保険においては、1級(最も重篤な場合)から12級(最も軽度な場合)まで、7つの段階に区分して等級認定が行われます。自賠責保険における等級認定は、基本的に、労災保険における等級認定基準(平成15年8月8日付厚生労働省労働基準局長通達「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」参照)に準じて行われます。
もっとも、自賠責保険においては、軽度の四肢麻痺(3級3号)や軽度の対麻痺(5級2号)に至らないより軽度な後遺障害(後遺症)の場合であっても、労災保険の認定基準に従って直ちに12級13号と認定されるわけではなく、麻痺や動作制限の程度や範囲に応じて、より柔軟に5級から9級までの等級が認定される場合があります。
自賠責保険と労災保険の認定基準を比較すると以下の表のとおりとなります。
| 自賠責施行令別表 | 労災補償障害認定基準 | |||||
| 四肢麻痺 | 対麻痺 | 単麻痺 | ||||
|
別表第1・1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの※1 |
高度 | 高度 | ||
|
中等度 かつ 常時介護 |
中等度 かつ 常時介護 |
|||||
|
別表第1・2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの※2 |
中等度 |
中等度 かつ 随時介護 |
|
|
|
軽度 かつ 随時介護 |
||||||
| 別表第2・3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のため労務に服することができないもの |
軽度 (但し、随時介護を要する場合を除く) |
中等度 (但し、常時介護、随時介護を要する場合を除く) |
|
|
| 別表第2・5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの | 軽度 |
高度 (―下肢) |
||
| 別表第2・7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 脊髄症状のため、軽易な労務のほかに服することができないもの※3 |
中等度 (―下肢) |
|||
| 別表第2・9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの※4 |
|
|
軽度 (―下肢) |
|
| 別表第2・12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの※5 |
・軽微な麻痺(運動性・支持性・巧緻性・速度についての支障がほとんど認められない程度) ・広範囲の感覚障害(運動障害なし) |
|||
(注)
※1 例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形等が認められるもの
※2 例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたため、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、脊柱の変形が認められるもの
※3 例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
※4 例:第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことにより一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度の遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるもの
※5 例:①軽微な筋緊張の亢進が認められるもの
②運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの
4.他の障害が併せて認められる場合の認定
脊髄損傷が生ずるケースでは、他の障害として、尿路障害、胸腹部臓器の障害、脊柱の変形、感覚障害、運動障害、さらには末梢神経系の障害などが併せて認められることがあります。
もっとも、脊髄障害は、通常、胸腹部臓器の障害や脊柱の変形障害・運動障害等を伴うものであるため、これらの障害も含めて先ほど述べた基準に従って等級の認定が行われています。そのため、これらの障害があったとしても、原則として併合の等級認定は行われませんが、これらの障害の等級が脊髄障害の等級よりも重い場合には、その重い障害も含めて総合的に評価し、等級認定がなされます。